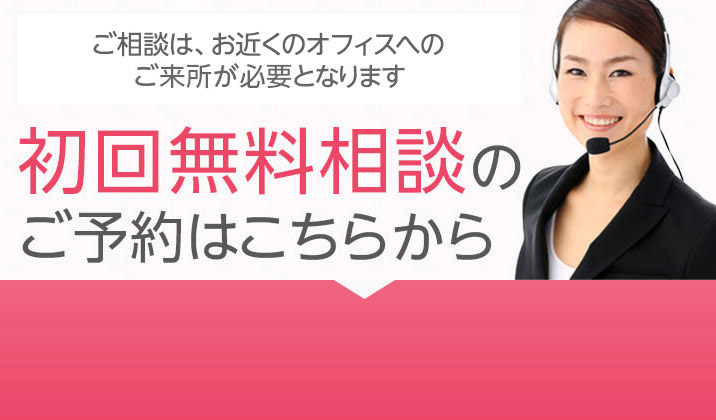児童手当は財産分与の対象? 子どもの資産を守るためにできること
- 財産分与
- 財産分与
- 児童手当

令和5年(2023年)の人口動態総覧によると、千葉県における同年中の離婚件数は2万3251件、人口1000人に対する離婚率は1.50となっています。全国平均の離婚率が1.52であることを考えると、千葉県民の離婚しやすさは平均的といえるでしょう。
夫婦が離婚をする際には、結婚生活を通じて共に築きあげてきた財産を公平に分ける必要があります。これが、「財産分与」と呼ばれる制度です。財産分与ではさまざまな種類の財産が対象となりますが、「児童手当」がどのように取り扱われるか、ご存じでしょうか?
子どもを育て続けていく親の側からすると、児童手当も、子どもを育てるために必要なお金として確保したいと思うはずです。この記事では、財産分与における児童手当の取り扱われ方などについて、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士が解説します。
出典:「令和5年人口動態統計の概況(確定数)」(厚生労働省)


1、離婚時の財産分与における各種財産の取り扱いについて
まずは、財産分与において夫婦が所有する各種財産がどのように取り扱われるのかについて、一般的な事柄から解説します。
-
(1)夫婦の共有財産は財産分与の対象となる
財産分与は、夫婦が共同で築いた財産を公平に分けることを目的としています。
したがって、財産分与の対象となるのは夫婦の共有財産のみです。
なお、形式上の所有権(名義)をどちらかが単独で有している場合であっても、夫婦の婚姻中に得た財産であれば、夫婦が共有する財産であると推定されることになります(民法第762条第2項参照)。 -
(2)どちらかの特有財産は財産分与の対象外
夫婦の共有とはみなされず、純粋に夫または妻が単独で所有しているとみなされる財産のことを、「特有財産」といいます(民法第762条第1項)。
特有財産に該当する財産は、以下の通りです。- ① 夫婦の一方が婚姻前から有する財産
- ② 夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産
ただし、②については前述の通り、夫婦の婚姻中に得た財産は夫婦の共有と推定されます。
このような財産について「自分のものである」と主張するためには、そのことを基礎づける事実を立証することが必要となります。 -
(3)住宅ローンなどのマイナス財産の取り扱いは?
上記で解説してきた共有財産・特有財産についての考え方は、借金などのマイナス財産についても当てはまります。
つまり、婚姻中に夫婦の共同生活のために負担した借金も、財産分与の対象になるのです。
逆に、婚姻前からの借金や、婚姻中であっても特にどちらか一方の自己責任で負担した借金などは、財産分与の対象外とされます。
たとえば、婚姻後に購入した住宅についての住宅ローンは、夫婦の共同生活のための借金と扱われて、財産分与の対象とされる可能性が高いでしょう。
ただし、住宅ローンは事実上、住宅の土地・建物とひもづいた借金という性質を有しています。
そのため、実際の財産分与の際には、住宅ローンは住宅が建っている土地や建物自体の価値と通算したうえで、夫婦間で精算されることが通常です。
2、児童手当は財産分与の対象か?
児童手当とは、子どもを育てる費用への援助として、自治体から毎月一定の金額が支給される制度です。
児童手当については、「子どものためのお金」というイメージが強いでしょう。
夫婦の財産を分ける財産分与の手続きで、児童手当がどのように取り扱われるかについて、解説します。
-
(1)児童手当の受給権者は誰?
児童手当の受給する権利を持つ「受給権者」は、中学校3年生修了前の子どもを養育している父母のうち、「主に生計を維持している」側となります。
「主に生計を維持している」ということの具体的な基準は、以下の通りです。【「主に生計を維持している側」の判断基準】
① 父母が別居している場合
子どもと同居している親が「主に生計を維持している」と判断されます。
② 父母が同居している場合
父母の所得を比べて、恒常的に所得が上回っている側が「主に生計を維持している」と判断されます。
なお、父母の所得がほぼ同じ場合には、以下の要素が考慮されます。
- 所得税の申告において、子どもの扶養控除が適用されているかどうか
- 勤務先で子どもについての家族給が支払われているかどうか
- 子どもを健康保険の被扶養者としているかどうか
児童手当の受給権者は、あくまでも父母のいずれかであり、子どもではありません。
そのため、児童手当として支給された金銭は、父母のいずれかが所有する財産であると解釈されることになるのです。 -
(2)児童手当は夫婦の共有財産|財産分与の対象になる
児童手当の受給権者は父母のいずれかになるものの、夫婦の共同生活において不可欠の要素を構成する「子どもの養育」を支給目的としています。
つまり、児童手当は夫婦の共有財産としての性質を有しているとみなされて、財産分与の対象になると考えられるのです。
ただし、夫婦が別居した後に支給される児童手当は、本来であれば子どもと同居している親が受け取り、生活費などとして活用すべきものです。
この点については、財産分与や婚姻費用の分担についての話し合い・調停などにおいて、具体的な事情に応じながら考慮することが望ましいでしょう。
3、児童手当以外の子どもに関する財産の財産分与における取り扱いは?
児童手当以外にも、学資保険・祖父母から両親への援助金・子どもがもらったお年玉やお小遣いなど、子どもに関連する財産にはさまざまな種類があります。
財産分与においてはそれぞれどのように取り扱われるか、解説していきます。
-
(1)学資保険の解約返戻金
学資保険に加入している場合、解約返戻金に関する債権が財産分与の対象になります。
仮に掛け金をどちらかが単独で負担していたとしても、学資保険は夫婦が共同の財産を原資として、子どものために加入・拠出したものと考えられます。
そのため、夫婦の共同財産とみなされる可能性が高いでしょう。 -
(2)祖父母から両親への援助金
祖父母から両親に対して、またはどちらか片方の親に対して贈与された、子どもを育てる援助金についても、財産分与の対象になるものと考えられます。
祖父母の側としては、嫁や婿ではなく、自分の子どもに対してだけ贈与するつもりだったという場合もあるでしょう。
しかし、子どもを育てるための資金であれば、夫婦の共同生活に対する援助金としての性質を有しますので、財産分与の対象になる可能性が高いといえるのです。 -
(3)子どもがもらったお年玉やお小遣い
子どもがもらったお年玉やお小遣いについては、基本的には「子どものもの」と考えるべきでしょう。
親の財産ではない以上、子どもがもらったお年玉やお小遣いは、財産分与の対象外と考えられます。
なお、たとえお年玉やお小遣いが親名義の口座に入金されているとしても、それはあくまで親が管理しているだけであって、子どものお金であることには変わりありません。
しかし、現実には、親名義の口座で管理されている場合には、お年玉やお小遣いとしてもらった金額がいくらであるかを特定するのが困難なケースが多いでしょう。
そのため、お年玉やお小遣いを親名義の口座で管理している場合には、もらった時期と金額がその都度記録してある場合でなければ、親の財産とまとめて財産分与の対象になってしまうことも考えられます。
4、財産分与を有利に進めるためにできること
離婚時の財産分与を有利に進めるために、財産分与を受ける側(財産が少ない側)ができることについて解説します。
-
(1)相手が持っている財産を正確に把握する
財産分与の話し合いは、まず、「夫婦の共有財産全体の金額」を明らかにすることから始まります。
その次に、「財産をどのように分けるか」を決定することになるのです。
財産分与を受ける側がもっとも不安に思うのは、「相手が財産を隠しているのではないか」や「自分が把握していない財産があるのではないか」ということでしょう。
もし財産の把握漏れがあると、その分、財産分与の金額も少なくなってしまいます。
そのため、相手が持っている財産を正確に把握することが重要になるのです。 -
(2)弁護士に相談する
そもそも相手が隠している財産が存在するかどうか、どのような財産を隠しているかということについては、そう簡単にはわからない場合が多いでしょう。
しっかりと財産調査を行うためには、専門家である弁護士に相談することが最適です。
ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士は、財産分与に関する豊富な経験を生かしながら、相手との交渉や各種照会・開示の手続きを利用して、適正な財産分与が行われるように依頼者をサポートいたします。
離婚を検討していて、財産分与の問題を抱えている方は、ぜひベリーベスト法律事務所にまでご相談ください。
お問い合わせください。
5、まとめ
児童手当は、子どもの父母のうちどちらかが単独で受給権者となります。
一方で、子どもの養育という夫婦共同生活の要素となる活動に対する援助金であるという性質も有しています。
そのため、離婚時の財産分与の際には、児童手当は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象になる可能性が高いといえるでしょう。
財産分与を受ける側にとっては、相手が所有している財産の全貌を正確に把握することが重要になります。
ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談をいただければ、離婚に関する養育費・婚姻費用・親権・慰謝料・財産分与などの交渉を有利に進めるため、専門家の視点から依頼者を全力でサポートいたします。
離婚問題についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスまで、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています