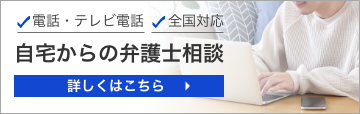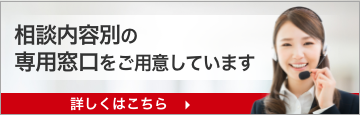令和元年の意匠法改正は何が変わった? 知っておきたいポイントを船橋の弁護士が解説
- 商標・特許・知的財産
- 意匠法
- 改正

令和元年に行われた意匠法の改正により、従来は対象にならなかった建築物や内装なども、意匠権で保護される対象となりました。
船橋市を走るJR総武線を有するJR東日本の建物も、意匠登録がなされたのです。
ものづくり企業、Web制作企業等においては、自社のデザインは財産であり、他者に模倣されることは許容しがたいものです。
知的財産にはいくつかの種類がありますが、意匠法は「デザイン」を守るために設けられている法律なのです。
意匠法の改正により、これまでは保護されなかった分野も保護されるようになり、知らずにいると被害者になるだけでなく、加害者になる可能性もあります。
本コラムでは意匠法の概要や法改正の基本的な情報から、意匠権を「侵害した場合」と「侵害された場合」のそれぞれの対処法について、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士が解説いたします。
1、意匠法とは? 意匠法の目的と概要
まずは、意匠法の目的や意匠法の概要を確認しておきましょう。
-
(1)意匠法とは?
「意匠」とは、家具や菓子などの製品のパッケージ、家電、日用品、機械、部品、容器などの商品に用いられる「デザイン」のことを指します。
これらのデザインが作り出されるまでには、企業や個人によって、多大な資源や時間が割かれています。そのデザインが模倣されてしまうと、デザインを作り出した側にとっては多大な損害となるでしょう。
そのため、デザインを作り出した側の権利を守る法律である「意匠法」が設けられているのです。
具体的には、意匠法の対象とされるデザインであり、意匠出願をして意匠登録が認められれば、そのデザインは「意匠権」によって保護されることになります。 -
(2)意匠登録するためには
意匠権を獲得するためには、意匠制度に従って「意匠登録」の出願を行わなければいけません。
意匠登録の出願は、特許庁に対して行います。
また、出願を行うためには、以下の条件を満たす必要があるのです。- 工業上利用できる意匠であること
- 今までにない新しい意匠であること
- 容易に創作することができないものであること
- 先に出願された意匠の一部と同一、類似していないこと
- 不登録事由に該当していないこと
- 意匠ごとに出願していること
- 他人よりも早く出願していること
これらの条件を全て満たしている場合には、「登録査定謄本」が送達されます。
登録料を支払えば、設定登録が行われ、意匠権が生じるようになるのです。
2、意匠法改正でどう変わった? 拡充された保護対象
令和元年4月1日、意匠法の改正が行われました。
技術や時代の変化により、「意匠権」の対象と見なして保護するデザインの範囲を拡大する必要性が高まっていたことを受けての改正となります。
-
(1)令和2年3月31日以前の意匠法改正前に保護されていた意匠
意匠法が改正される前の意匠法での保護対象は、「物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合」と規定されていました。
この規定は、意匠権の対象となるものは「工業デザイン」である、という想定に基づいています。具体的には、飲料や食品のパッケージ、家電や自動車のデザイン、化粧品のパッケージ、機械部品や衣服、アクセサリー等、家具や住宅設備などが、意匠権の対象として保護されるべきものであると見なされていたのです。
一方で、Webページの画像や、建築物のデザインなどは「物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合」に該当しません。そのため、これらは意匠法による保護の対象とされていなかったのです。 -
(2)令和2年4月1日以降の意匠法改正後に保護されるようになった意匠
意匠法改正によって、保護の対象となるデザインが拡大されました。
ただし、法改正によって新たに意匠法で保護されることになった製品を自社で取り扱っている場合には、速やかに意匠登録を行わなければ、他社にデザインを模倣されたうえに意匠登録を先にされてしまうおそれがあるのです。
【意匠法改正によって、新たに保護対象となったデザイン】
・Webサイトの画像
これまでも、「製品に伴って映し出される画像」(スマートフォンに表示されるアイコン)などは意匠法による保護の対象となっていました。
そして、今回の法改正では、「製品と関連しない画像」も保護の対象となったのです。
具体的には、「ホームページの画像」や「商品購入用ページの画像」などのWebサイトの画像が、保護されるようになりました。
・建築物
建築物の外観のデザインも意匠法によって保護されることになりました。
大手アパレルチェーンの店舗や、JR東日本の上野駅の駅舎などが、すでに意匠登録されています。
・内装
内装とは、建物の「内部の統一されたデザイン」のことをいいます。壁紙や床材、住宅設備や家具などを含めた建物の内部の空間のデザイン全体が、意匠法による保護の対象になったのです。
・組物の部分意匠の登録が可能になった
意匠法改正により、「組物」の意匠登録が可能となりました。
組物については、意匠法8条で以下の通り規定されています。
「同時に使用される2以上の物品であって経済産業省令で定めるものを構成する物品にかかる意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる」
組物の具体的な例としては「ダイニングテーブルとダイニングチェアのセット」や「オフィスデスクとオフィスチェアのセット」などがあります。
3、その他、主な改正ポイントとは
今回の意匠法改正では、意匠法の保護となる対象が拡充しただけでなく、「関連意匠制度」も拡充しました。
-
(1)関連意匠制度とは? 関連意匠制度の概要
関連意匠制度とは、同じ出願人の類似している意匠のひとつを「本意匠」、残りを「関連意匠」として登録できる制度のことです。
家電や家具、自動車などの工業製品では、最初のデザインコンセプトを基に、さまざまな種類のデザインが制作されることがあります。
関連意匠制度により、最初に意匠登録をしたものを、「本意匠」として、類似している派生製品を「関連意匠」として意匠出願をすることができるのです。 -
(2)関連意匠制度の改正ポイント
今回の意匠法の改正では、関連意匠制度が使用しやすくなりました。
・関連意匠の出願可能期限
従来の関連意匠制度では、関連意匠の出願が可能なタイミングは「本意匠の意匠公報発行前まで」に限定されていました。
今回の改正では、「本意匠の出願日から10年を経過する日の前まで」と、出願可能な期限が大幅に延長されたのです。
・関連意匠を本意匠とした関連意匠の出願も可能
これまでは、本意匠に類似していない、関連意匠に類似しているデザインについては関連意匠としての登録ができませんでした。
しかし、今回の意匠法改正により、「関連意匠を本意匠にした、関連意匠」の出願も可能になったのです。
4、意匠権を侵害したら? 侵害されたら? 意匠権トラブルの対処法
事業においては、意匠権の存在を知らずに、他社や他人の意匠権を侵害してしまうことがあります。逆に、他社によって自社の意匠権が侵害されてしまう可能性もあるのでしょう。
意匠権に関するトラブルが発生した場合の対処法について、解説いたします。
-
(1)意匠権を侵害したらどうすれば?
他社の意匠権を侵害してしまった場合には、意匠権侵害行為を停止するよう、意匠権者が申し立てを行う可能性が高いでしょう。
また、意匠権の侵害により相手に対して損害を生じさせてしまった場合には、損害賠償が請求されるおそれもあります。
また、悪質な意匠侵害である場合には、警察に被害届や告訴状を提出されて、刑事告訴の対象となるリスクもあるのです。
意匠権侵害で有罪判決を言い渡された場合、意匠法六十九条により「10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金」のいずれか、もしくは両方の刑罰が科されます。さらに、意匠法七十四条により、意匠侵害を行った法人には最大で3億円の罰金が科される可能性があります。
悪意はなかった場合であっても、意匠権を侵害してしまった場合には、訴訟や刑事告訴などに発展する前に意匠権者との和解を行うことが重要になります。訴訟になった時点で、「意匠侵害をした会社だ」ということが世間に知られてしまい、風評被害のリスクが生じるからです。
和解を適切に進めるためには、自社の経営者や社員ではなく、経験が豊富な専門家に交渉を担当させることが最善です。知的財産に関係する企業法務を取り扱っている弁護士に相談しましょう。 -
(2)意匠権を侵害されたらどうすれば?
自社の意匠権が他社に侵害されていることが判明してしまった場合は、以下の処置をとることを検討しましょう。
- 意匠権侵害の差し止め請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
また、意匠権を侵害していることを申し入れて、先方が誤りを認めた場合には、示談交渉によって解決することも可能です。
ただし、自社に損害が発生している場合には、必ず損害賠償請求を行うべきでしょう。
相手方との示談交渉を行う前には、事前に弁護士に相談して、請求する賠償金の適正な金額について聞いておく必要があります。また、示談交渉では相手側が弁護士に交渉を任せる可能性が高いため、自社の方でも弁護士に交渉を代行させたほうがよいでしょう。 -
(3)意匠出願、登録をしていない製品やデザイン等が模倣された場合
意匠の出願には手間がかかることから、自社で取り扱っている一部の商品のみしか意匠登録を行っていない、という企業は多いでしょう。
しかし、原則として、デザインは意匠が登録されるまでは法律で保護されません。
そのため、意匠登録をしていない商品や製品には、競合他社に模倣されてしまうリスクが潜在しているのです。
このような場合、意匠権侵害を問うことはできませんが、「不正競争防止法2条1条3号」に基づく、他社の製品の販売停止を請求できる可能性があります。
ただし、不正競争防止法に基づく販売停止の請求が認められるのは、「製品が販売されてから3年以内」に限られています。もし意匠登録がなされていない製品を模倣されてしまった場合には、速やかに弁護士に相談して、販売停止の請求を行いましょう。
5、まとめ
意匠法改正により、これまで保護されていなかったWebサイトの画像、建築物の外観や内装なども、意匠法による保護が受けられるようになりました。
意匠法改正の恩恵を受けるためには、これらのデザインについて意匠出願を行うことが必要となります。
意匠出願は、原則として先着順であるため、意匠出願が遅れてしまうと他社に自社デザイン等を模倣されてしまうリスクがあります。
意匠法改正により、自社製品のデザインなどが新たに保護の対象になった場合は、速やかに意匠出願を行いましょう。
ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスでは、意匠法改正により生じた意匠権侵害に関するご相談を受け付けております。また、ベリーベストグループには特許事務所も含まれており、弁理士と弁護士が連携したワンストップサービスを提供しております。
他社の意匠を侵害してしまった方、逆に自社の意匠を侵害されてしまった方は、ぜひ、べリーベスト法律事務所 船橋オフィスにまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています