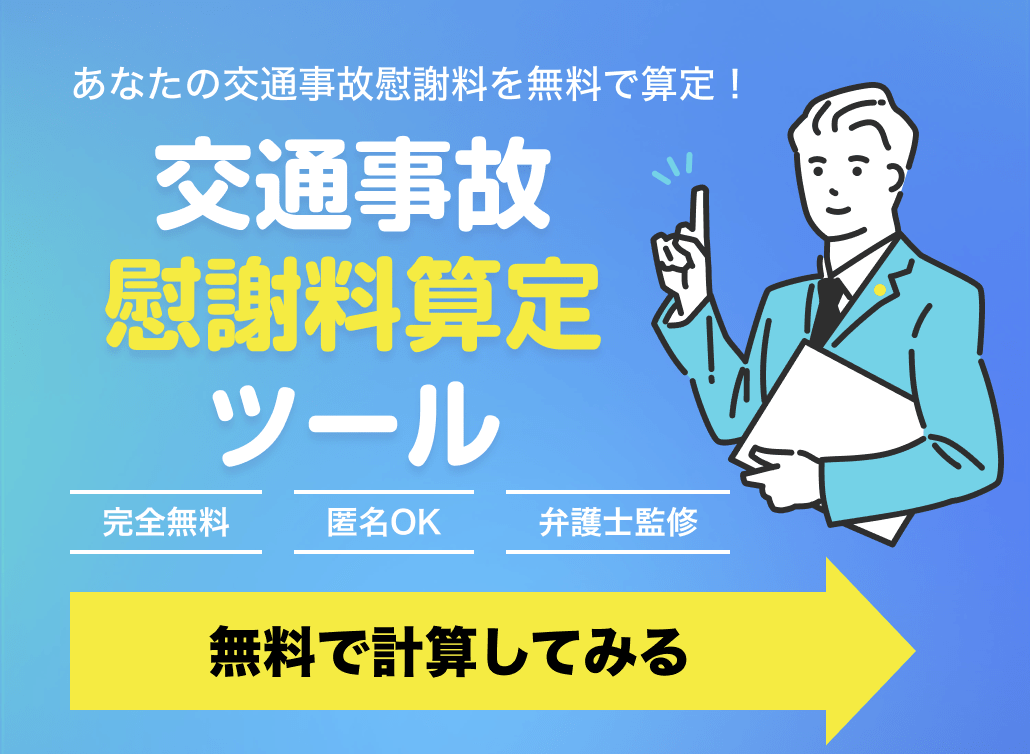交通事故でくも膜下出血になって後遺症が残ったとき、慰謝料を請求する方法
- 後遺障害
- くも膜下出血
- 事故

船橋市がまとめた統計によると、平成23年から平成27年の過去5年間に船橋市で起きた交通事故発生件数、およびその死者数と負傷者数年間の平均値は、発生件数が年間で1,769件、死者数が年間10人、そして負傷者が年間2,082人となっています。
交通事故の被害で、くも膜下出血になってしまった場合、高次脳機能障害や意識障害などの重い後遺症が残ってしまうおそれがあるだけでなく、死に至るケースも多く存在します。
事故により後遺症を負った被害者は、加害者に対して後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求することができます。しかし、そのためには、適切な「後遺障害等級」の認定を受けることが重要です。
本コラムでは、くも膜下出血により後遺症が残った場合に適切な後遺障害等級の認定を受ける方法や、示談交渉の注意点について、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士が解説いたします。
1、くも膜下出血の症状と後遺障害
-
(1)くも膜下出血とは
人間の脳は頭蓋骨のなかにありますが、頭蓋骨と脳との間には、硬膜・くも膜・軟膜という三つの膜が存在します。
そして、くも膜と軟膜の間にある空間は、「くも膜下腔」と呼ばれ、「くも膜下出血」とは、この「くも膜下腔」に出血が起きている状態のことをいいます。 -
(2)くも膜下出血の症状
くも膜下出血の代表的な症状は、下記の通りになります。
- 突然の激しい頭痛
- 意識がもうろうとする、意識を失う(意識障害)
- 吐き気、嘔吐
とくに、くも膜下出血によって生じる頭痛は「バットで殴られたような痛み」と表現されるほど激しいものであり、痛みによって気絶してしまう場合もあるといわれています。
-
(3)くも膜下出血の後遺障害
くも膜下出血になってしまうと、下記のような後遺障害が残るおそれがあります。
● 遷延性意識障害
遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことを指します。慢性的な昏睡状態が続き、常に介護が必要な状態となります。
● 高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、脳の損傷により、脳の高次脳機能に発生した障害のことをいいます。
高次脳機能障害の主な症状として、知的障害や社会的行動障害が挙げられます。しかし、高次脳機能障害は「目に見えない障害」とも呼ばれており、外見からはとくに障害が発生していることが判別できません。そのため、障害によって言動に影響が生じているということが周囲に理解されづらい、という問題があります。また、障害の存在を立証することも難しいため、後遺障害等級の認定手続きでも困難を伴うことがあります。
● 麻痺
脳の損傷により、身体に麻痺が残ってしまうことがあります。
どこに麻痺が生じるかということは受傷箇所によっても異なりますが、顔や手足などの一部に麻痺が残るだけでなく、より広範囲に麻痺が残ってしまうケースもあります。
● 外傷性てんかん
脳の損傷により、意識消失やけいれん、身体のこわばりなどの症状が発作的に発生する場合があります。これらの症状は「外傷性てんかん」と呼ばれます。
外傷性てんかんは、投薬により発作をコントロールすることになりますが、症状の程度によっては就労に制限を受けるような後遺障害となる場合があります。
● 視力障害
上記各症状のほか、場合によっては、失明または視力低下などの後遺障害が残るおそれもあります。
2、後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級の認定には、「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という審査機関に後遺障害等級の認定を申請する手続きが必要となります。
後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」という二つの方法があります。以下では、それぞれの方法のメリットとデメリットについて、詳しく解説いたします。
-
(1)事前認定
「事前認定」では、事故を起こした加害者側の任意保険会社が、後遺障害等級認定に必要とされる手続きをすべて行います。
大部分の手続きを保険会社に任せることができるので、被害者の手間や負担がかからないという点がメリットになります。
一方で、実際に損害賠償金を払うのは加害者側の保険会社であるため、事前認定では、「等級が認定されなかったり、低い等級が認定されたりしたほうが支出を抑えることができる」という側によって申請が行われてしまうことになります。
審査機関に提出する診断書などの資料も、加害者側の保険会社によって準備されますが、申請に最低限必要な書類以外にどのような資料を提出するかについては保険会社に委ねられることとなります。そのため、有利な資料を提出して等級が認定される可能性を高めるなどの対策を被害者側から行うことができないという点がデメリットになります。 -
(2)被害者請求
「被害者請求」では、被害者の側で書類や証拠を準備して、加害者の自賠責保険会社に対して保険金を請求して、後遺障害等級の認定を申請する手続きを行います。
事前認定とは異なり、交通事故証明書や診断書をはじめとする様々な資料を被害者側で収集する必要があり、手間がかかるという点はデメリットといえるでしょう。
しかし、被害者請求では、等級が認定される可能性を高められるような有利な資料を提出できる、という点が大きなメリットとなります。
後遺障害等級が認定されるか否か及び認定された後遺障害等級が何級なのかということは、加害者に請求できる損害賠償の金額を大きく左右します。そのため、後遺障害等級の申請は事前認定ではなく被害者請求で行うことをおすすめします。
そして、弁護士に依頼をすれば、被害者請求のために必要となる資料の収集や申請の手続きなどを代理させることができます。これにより、「手間がかかる」というデメリットも解消しつつ、等級認定に向けて積極的に動くことができるのです。
3、後遺障害慰謝料と逸失利益
後遺障害等級が認められた場合には、基本的に、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という費目についても賠償されることとなります。
これらの費目はどのような損害に対する賠償であるのか、金額はどのように定められるのか、という点について解説いたします。
-
(1)後遺障害慰謝料
「慰謝料」とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。
そして、「後遺障害慰謝料」とは、事故により後遺障害が残ったことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料となります。
なお、後遺障害が残らない場合であっても、交通事故により負ったケガに対しては「傷害慰謝料」を請求することができます。
後遺障害慰謝料や傷害慰謝料の金額の算定方法には、自賠責保険基準と任意保険基準、そして裁判所基準という、三種類の基準が存在します。
自賠責保険基準は、被害者に対する最低限の補償を担保するための強制保険である、自動車損害賠償責任保険で用いられる基準となります。あくまで最低限の補償であるため、その金額は、三つの基準のなかでも最も安いものとなります。
任意保険基準は、任意保険会社で用いられる基準のことを指し、保険会社によって金額の基準は異なります。任意保険基準については、自賠責保険基準よりは高額となることが多いですが、後述する裁判所基準よりは低い基準となっています。
裁判所基準とは、過去の裁判例の集積をもとに定められた基準のことです。大半の場合において、三つの基準のなかで最も高額となります。ただし、保険会社が被害者本人との交渉段階において裁判所基準での賠償に応じる可能性は低く、裁判所基準で示談交渉をする場合には、弁護士に依頼することによるのが現実的です。
なお、いずれの基準においても、後遺障害等級が高ければ高いほど、後遺障害慰謝料の金額も高くなります。 -
(2)逸失利益
逸失利益とは、後遺障害を負わなければ、本来得られていたはずである、将来の収入(利益)のことを指します。
基本的に、逸失利益の金額は、後遺障害等級ごとに定められた「労働能力喪失率」と被害者自身の収入、そして労働能力喪失期間という、三つの要素から算定されます。
原則として、労働能力喪失率に、事故直前の被害者の収入をベースとして算定される「基礎収入額」、そして被害者の症状が固定してから67歳を迎えるまでの年数である「労働能力喪失期間」をかけて計算したものが損害となりますが、逸失利益は将来発生する損害であり、それを前倒しで受け取ることになることから、将来分の利息を控除します。
将来利息控除の計算は複雑であるため、実務上は労働能力喪失期間に対応する「ライプニッツ係数」を用いて、基礎収入額×労働能力喪失率×ライプニッツ係数の方法で計算されます。
なお、逸失利益は、会社員・アルバイト・自営業者・フリーランスなどの職業にかかわらず請求できます。専業主婦(主夫)や子どもが事故にあった場合も、「賃金センサス」などの統計情報を用いて計算することが可能です。
ただし、事故当時に無収入であった場合や、生活保護受給者である場合に、今後収入を得られるという見込みが無ければ、基礎収入額が0と扱われ、逸失利益の賠償を受けられない可能性があります。
また、労働能力喪失率は、後遺障害の種類と被害者の職業やその具体的な内容等の兼ね合いによって増減する場合があり、これによって逸失利益の金額が大きく変わる場合もあります。
4、くも膜下出血の示談や後遺障害等級の異議申立ては弁護士に相談
-
(1)示談交渉は弁護士に依頼したほうがよい
交渉相手である加害者側の保険会社は、交通事故の示談交渉のプロであり、慰謝料の相場や過失割合など、交通事故に関する専門知識も豊富に持っています。そのため、交渉に慣れていない被害者の方が個人で示談交渉を行うと、自分の利益や権利を正当に主張することができなかったり、知らず知らずのうちに示談金の金額が減らされたりするなどして、不利な結果につながる可能性があります。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、事故の状況に関する詳細な情報から過去の裁判例まで、様々な側面を考慮しながら、最も高額な裁判所基準を前提に、専門知識に基づいた適切な主張を行うことが可能になります。 -
(2)後遺障害等級の認定結果に不服がある場合も弁護士に依頼すべき
事前認定で申請を行った場合やご自身で被害者請求を行った場合、後遺障害等級が認定されなかったり、低い等級が認定されたりするおそれがあります。
後遺障害等級の認定の結果に不服がある場合には、「異議申立て」を行うことができます。
ただし、一度出された認定結果を変えるためには、異議申立ての理由を説明するだけでは足りず、最初の申請の時点では提出されていなかった、追加資料の提出を検討すべき場合もあります。
弁護士に依頼をすれば、弁護士において資料や後遺障害等級の認定内容を分析し、どのような観点での補充が必要であるかを検討したうえで、適切に異議申立てを行うので、後遺障害等級認定の可能性を上げることができます。
5、まとめ
くも膜下出血は、重い後遺症が残る可能性の高いケガです。事故によりくも膜下出血となってしまった被害者が、後遺障害慰謝料や逸失利益を含めた損害賠償を加害者に請求する権利を行使するためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが極めて重要となります。
後遺障害等級は、加害者側の保険会社に申請を任せる「事前認定」で行うと、認定されるべき等級が認定されなかったり、低い等級が認定されたりする可能性があります。そのため、弁護士に相談したうえで、適切な後遺障害等級の認定を受けられるよう対応する必要があります。
千葉県や近隣県で交通事故の被害に遭った方や被害者のご家族は、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスにまでご相談ください。交通事故案件や後遺障害等級の申請・異議申立ての経験豊富なべリーベストの弁護士が、親身に対応いたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています