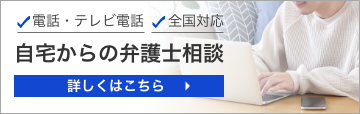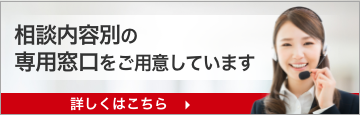講座を途中解約して、ローンの支払いを止めることができた事案
- CASE1310
- 2025年10月17日更新

- 個人
- 資格商法
- 特定商取引法
- 女性
ご相談内容
Aさんは、転職を考え、自己研鑽のため、B社のオンラインの講座を受けようと思い、同講座を申し込みました。同講座は特定の回数、オンラインで受けるというものでしたが、特に書面資料等はなく、オンラインの面談・相談を受けるというものでした。総額は100万円ほどの講座でしたが、講座受講のためにAさんは、C社と130万円ほどのローン契約までしてしまいました。
B社の講座を何回か受けたところ、Aさんは講座受講を辞めたいと考えるようになりました。そのため、B社に講座の受講を辞めたいということを伝え、その後、実際に講座を受けていませんでした。
その後、Aさんは、C社から、ローンの残額を全て支払うことを請求され、どうしたら良いか分からなくなり、当事務所に相談に来られました。
ベリーベストの対応とその結果
まず、Aさんの受講していた講座は、「特定商取引法」上の「特定継続的役務提供」と呼ばれる契約に当たる講座ではありませんでした。加え、契約書には、サービス対価を減額できない旨の条項が入っており、この契約書にAさんはサインしてしまっていました。
しかしながら、Aさんは実際に講座を受けておらず、また、講座自体は特に資料等が配られる講義形式の講座ではなくて、いわゆる面談形式で特定回数の相談ができる、といった形の役務内容でした。
こうしたことから、Aさんが受講していない講座部分については、実際に相談を行っていない以上、何らの便益をAさんが受けていないと言える状況であったため、未提供役務部分の対価の保持を事業者に認めることは、消費者の権利を一方的にかつ大きく制限するものといえる状況でした。
そのため、この点を主張し、Aさんが受講していない講座(役務)部分については、Aさんが対価を支払う必要がないことを主張し、B社(役務提供会社)及びC社(ローン会社)に交渉を行ったところ、ローンを組む際の手数料部分や既に受講した講座のサービスの対価部分はともかく、受講していない講座のサービス対価を支払わない旨の合意を行うことができました。
しかしながら、Aさんは実際に講座を受けておらず、また、講座自体は特に資料等が配られる講義形式の講座ではなくて、いわゆる面談形式で特定回数の相談ができる、といった形の役務内容でした。
こうしたことから、Aさんが受講していない講座部分については、実際に相談を行っていない以上、何らの便益をAさんが受けていないと言える状況であったため、未提供役務部分の対価の保持を事業者に認めることは、消費者の権利を一方的にかつ大きく制限するものといえる状況でした。
そのため、この点を主張し、Aさんが受講していない講座(役務)部分については、Aさんが対価を支払う必要がないことを主張し、B社(役務提供会社)及びC社(ローン会社)に交渉を行ったところ、ローンを組む際の手数料部分や既に受講した講座のサービスの対価部分はともかく、受講していない講座のサービス対価を支払わない旨の合意を行うことができました。
解決のポイント
講座の契約書には「返金しません」、「減額しません」などと書かれていることがあり、こうした契約書にサインをしてしまった場合、消費者側から返金を求めることができない、と思ってしまうことはあると思います。
しかしながら、事業者が、契約書などで一方的に消費者が解約できないようにしたり、返金や減額をできないようにすることは、場合によっては消費者を一方的に不利にし、契約を途中でやめることを妨害するものとして、無効となることも多々あります。
そのため、契約書に解約不可、返金しない、減額しないなどと書かれていても、サービスの内容やその料金等によっては、解約したり、解約の上で返金を求めたり、解約の上で減額を求めたりすることができることがあります。
もっとも、講座に関してテキストが存在していたり、講座がオンラインでいつでも閲覧できるような形式になっていたりした場合は、「提供していないサービスの対価を消費者に支払うように求める、一方的に消費者に不利な契約」とまでは言えない場合があり、実際の受講がなかったとしても、返金や減額を求められない可能性もありますので、注意が必要です。
しかしながら、事業者が、契約書などで一方的に消費者が解約できないようにしたり、返金や減額をできないようにすることは、場合によっては消費者を一方的に不利にし、契約を途中でやめることを妨害するものとして、無効となることも多々あります。
そのため、契約書に解約不可、返金しない、減額しないなどと書かれていても、サービスの内容やその料金等によっては、解約したり、解約の上で返金を求めたり、解約の上で減額を求めたりすることができることがあります。
もっとも、講座に関してテキストが存在していたり、講座がオンラインでいつでも閲覧できるような形式になっていたりした場合は、「提供していないサービスの対価を消費者に支払うように求める、一方的に消費者に不利な契約」とまでは言えない場合があり、実際の受講がなかったとしても、返金や減額を求められない可能性もありますので、注意が必要です。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)